【あがり症で声が震える】克服のための3つのポイント
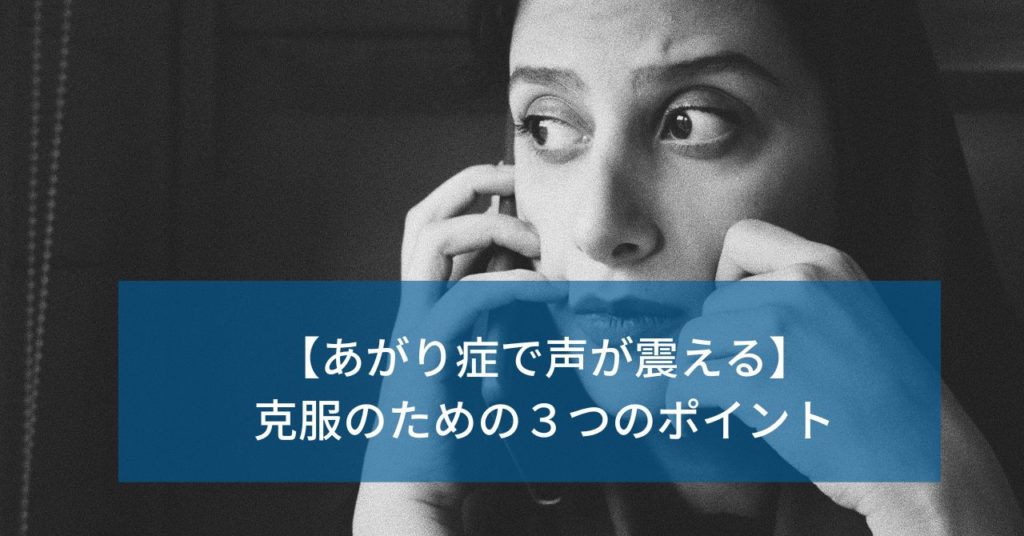
公認心理師の藤井です。あがり症でこのようなお悩みはありませんか?
- 人前で話す時に声や手が震える。
- 緊張してとにかく汗をかいてしまう。
- あがってしまい不安や緊張が強い。
- あがってしまうので、論理的に話すことが出来ない。
これらは、あがり症特有の悩みです。あがり症は社交不安症(社交不安障害)ともいいます。このあがり症克服のために3つのポイントを解説します。ポイントは科学的に効果が実証されている認知行動療法をベースにした内容になります。この記事を読むと、あがり症(社交不安症)克服のポイントを知ることが出来ます。
目次
【ポイント①】「あがり」は必要。「あがり」に囚われすぎているのが問題
あがり症や社交不安症で悩まれている方は、「あがり」が高くなっています。「あがりを無くそう」「あがりを減らそう」と考えがちです。すでにこの状態が「あがりに囚われている状態」であるのです。「あがり」を意識過ぎているのです。意識しすぎているので、「あがり」やすくなります。
「あがり」はゼロにならない ゼロにしようとしてはいけない
「あがる」こと自体は悪いことではありません。あまりにリラックスしすぎていたら緊張感もなくなります。結果的にダラダラしすぎてプレゼンやスピーチがうまくいなないでしょう。ある程度「あがり」があるからこそ頑張れるのです。それに「あがり」や「緊張」は人間がもともと持っている行動です。ゼロにはなりません。
「あがり」は自分の身体が臨戦態勢に入っている証拠
「あがり」が高まっている状況というのは、身体が活性化している証拠です。あがると汗をかいたり、顔が紅潮したり、喉が渇く場合があります。震えが起きる場合もあるでしょう。これらはパフォーマンスをあげるために身体が覚醒しつつあるわけです。エンジンをふかしているようなイメージを持ってください。「あがり」の研究によれば、パフォーマンスを達成するには一定の「あがり」が必要とも言われています。
【ポイント②】「あがりをゼロにしたい」から「あがったまま行動しよう」へ
「あがり」をゼロにしようとすると益々不安になり、あがりやすくなる
あがり症がひどい時は、「あがりを何とかしよう!」「緊張して声が震えているかもしれない!」「不安から逃げたい!」という思いが強くなると思います。その思いの通りに行動したり、「あがり」をまぎらわせようとすると益々不安が強くなります。
「あがり」と日常生活はあんまり関係が無い
「あがり」が強いと日常の全て、自分の行動の全てについて「あがり」と結びつけてしまいます。「あがり」が無くなったら自由になれるのにと思いがちです。「あがり」が無くなれば、冷や汗や手の震えや声の震えも無くなるだろうと考えがちです。「あがり」があなたの日常や行動を支配しつつあるのです。
安心していただきたいのは、「あがり」と日常生活には関係があまり無いのです。あがってしまうのが怖いのでスピーチやプレゼンの場面を避けていませんか?避けているということは「あがり」の支配下に入りつつあります。支配下を脱するには、「あがり」に関係なく日常生活を楽しむと良いのです。また「あがり」が心配なので避けていることをあえてやってみる、「あがっている状態」のまま、あえてスピーチやプレゼンに臨むとかなり良いです。ただ、いきなり難易度の高い場面に臨むことは控えましょう。少し頑張ればやれそうなところからやっていきましょう。
【ポイント③】「あがりながら」「あがり症のまま」の状態で生活しよう。
あがり症が治ったら「あれをしよう」「これをしよう」という考えが、「あがり」に支配されています。あがったままの状態、「あがり」をそのままにして自分のやってみたいこと、避けていること、チャレンジしたいことに挑戦するのです。これが「あがり症」改善の最重要ポイントです。あがり症を治そうと頭の中で「あがり」のことを考え続けていませんか?「あがり」を減らそうと躍起になっていませんか?まずは発想を転換して、「あがったままの状態で行動する。生活する」と考えてみてください。
まとめ
あがり症克服のためのポイントをお伝えしました。今回お伝えしたポイントは心構えのようなものです。この心構えがあがり症克服のポイントとなります。ポイントを再度お伝えします。
- あがりは必要。あがりに囚われすぎてはいけない。
- あがりをゼロにしようとしてはいけない
- 「あがり症のまま」「あがったまま」で生活しよう。
最後に宣伝です。kiyokiyo(きよきよ)は、社交不安障害(スピーチ恐怖症・社会不安症・あがり症・対人恐怖症)を専門とした心理カウンセリングルームです。公認心理師・臨床心理士が運営しております。認知行動療法やLINE・Zoomでのカウンセリングを提供しておりますので、もし専門家のサポートが必要な方はカウンセラープロフィールやメニューをご確認の上、ご利用案内に沿ってお問い合わせください。
この記事の筆者
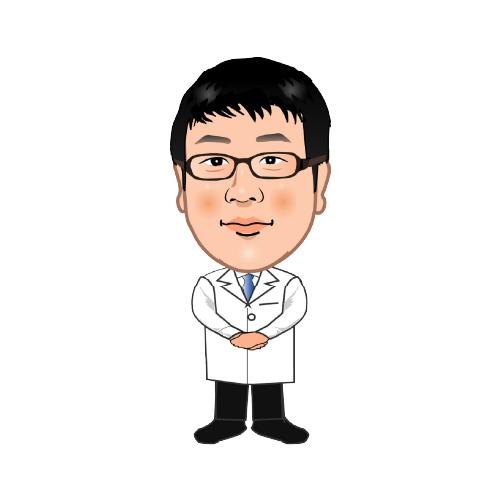
公認心理師・臨床心理士。社交不安症(障害)の認知行動療法を専門とする。首都圏の精神科病院、カウンセリングルーム、メンタルクリニックにてカウンセリング、復職支援、心理検査等を担当。
